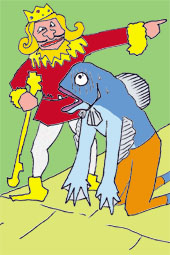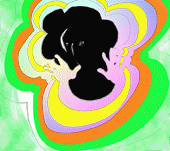|
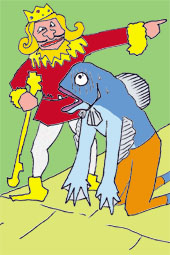
シチリアはメッシーナにコーラという名の息子を持つ母親がいました。コーラは朝から晩までずっと海で泳いでいる子供でした。
「コーラ! コーラ! 陸にお上がり! 魚じゃあるまいに、まったく! 」
いくら母親が海岸から呼んでも、コーラはどんどん遠くに泳いでいってしまいます。かわいそうな母親は叫びすぎて、お腹がいたくなってしまいました。
ある日のこと、大声で息子を呼び続け、もうやりきれなくった哀れな母親は、とうとう息子に呪いの言葉を投げました
「コーラ! お前なんぞ、魚になっちまうがいい! 」
その日は天の門が開いていたものと見え、母親の呪いはかなってしまいました。一瞬にして、コーラは半分人間で半分魚の姿になりました。手のひらはアヒルの水かきの様、声はまるでカエルの様。コーラは海で暮らすようになり、絶望した母親はそれからまもなく死んでしまいました。
メッシーナの海に半魚人がいるという知らせは王様にまで届きました。王様は全ての船乗りに、魚のコーラを見た者は王様がコーラと話しをしたがっていることを伝えるように命じました。
ある日、一人の水夫が船で沖に向かう途中に近くを泳いでいるコーラを見かけて、
「コーラ、メッシーナの王様がおまえと話しをしたいそうだ! 」と告げました。
すぐに、魚のコーラは王様の宮殿に向かって泳いでいきました。
王様は笑顔でコーラにこう言いました、
「魚のコーラよ、おまえほど泳ぎの達者なものはいない。このシチリアを泳いで一周し、どこの海が一番深いか、またそこに何が見えるかを報告するがよい。」
魚のコーラは命令に従い、シチリアを一周し、あっという間に帰ってきました。そして王様に、海の底で彼は山や谷そして洞窟やあらゆる種類の魚を見たけれども、メッシーナの岬の灯台を通りすぎた時だけは海の底が見えなかったので、こわかったと語りました。
「それでは、メッシーナの町は一体何の上に立っているのだ? 」王は尋ねました、
「もぐっていって何がこの町を支えているのか見て来るのだ」
コーラはまた潜って行って、丸一日帰りませんでした。そうして、ようやく浮かんでくると王様にこう告げました。
「メッシーナは大きな岩の上にあって、その岩は三本の円柱に支えられています。円柱の一つは丈夫で、もう一本はひび割れており、最後の一本は折れています。」
メッシーナ ああ、我がメッシーナ!
その内にお前はメスキーナ(没落するだろう)!
王様は大変驚いてしました。そして、今度はナポリの海の火山の底を知りたくなりました。 コーラは海に潜り、帰ってくると、まず冷たい水があり、それから熱い水になり、 ある深さに達したところではぬるい水も湧いていたと王様に語りました。 けれども王様が信じようといなかったので、コーラは二つの瓶を用意して貰うと、 再び潜って熱い水とぬるい水を瓶にいれて帰ってきました。
岬の灯台の海は底が知れないという知らせは王様を落ち着かせませんでした。そこで、コーラをまたメッシーナに連れて帰ると、こう言いました
「コーラよ、大体でも良いからお前はこの海の深さを私に教えなければならない。」
コーラは海に潜ると、二日後に帰ってきて、海の深くの岩盤から煙の柱が立ち昇っているため、水が濁ってしまって底は見えなかったといいました。
好奇心をおさえ切れなくなった王様はコーラに、
「灯台の上から飛び降り、もっと深く潜るがよい! 」と命じました。
灯台は岬の突端に立っていて、かつては灯台の番人がいました。番人は知らせがあるとラッパを吹き鳴らし、沖を艦隊が通ると旗を揚げて皆に知らせていました。
魚のコーラは灯台の上から、海に向かって飛び込みました。一日、二日、三日と王様は待ちましたが、コーラは帰ってきませんでした。四日目にようやく水から顔を出したコーラは、死人のように真っ青でした。
「どうした、コーラ? 」王様は尋ねました。
「死ぬほどおっかない目に会いましたよ。」コーラは答えました、
「一口で大きな船を飲み込んでしまうくらい大きい魚がいて、私は飲み込まれないように必死でメッシーナを支える柱の一つの後に隠れていました! 」
王様は驚きに口を閉じるのを忘れてしまいました。それでも、岬の海の深さを知りたいという好奇心は消えませんでした。コーラは、
「勘弁してください、もう私は潜りませんよ、こわいんです。」といいました。
どうしても、コーラを説得することが出来ない王様は、高価な宝石のたくさんついた冠を頭からはずすと、海に投げました。そして、
「取ってこい、コーラ! 」と言いました。
「何をするんです王様! 王国の冠を! 」
「二つとない冠だ、コーラよお前が潜って取りに行かなければならないぞ! 」
コーラは言いました、
「どうしてもと言われるのであれば、潜りましょう。けれど、私の心臓はもう二度と帰ってこれないと告げています。どうか私に一握りのレンズ豆をください。もし、運があれば、私が浮かんでくるでしょう。けれど、浮かんでくるのがレンズ豆であれば私はもう戻らないということです。」
レンズ豆が与えられ、コーラは潜っていきました。
待って待ち続けて、長いこと待った末に浮かんできたのは、レンズ豆でした。人々は魚のコーラの帰りを今も待ち続けているとのことです。
|